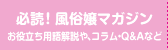HOME > 風俗嬢コラム Worker's Live!! > アトピー性皮膚炎とわたし
| アトピー性皮膚炎とわたし |  |
|---|
以前指名してくれていたお客さんに、小さな頃にひどいアトピーだった、というひとがいた。
かかった病院は数知れず、おうちには当時まだ珍しかった浄水器と空気清浄機。幼い彼はまずくて高価な健康食品をあれもこれもと食べさせられ、夏休みには地方のお寺で過ごす合宿にまで連れていかれたという。
「朝起きるとシーツが血だらけとか普通で」と笑い話のように言われてもそれがどんなものかうまく想像できない。なんなのそれ、怖い、そんなことあるの、と眉根を寄せるわたしに彼は、いやもうまるっきりホラーだよ、と笑ってみせた。
症状は成長するにつれ徐々に落ち着いていったそうで、よかったね、ほんとうによかった、よくなってよかった、とわたしはシワを寄せたまま言った。
途中おふくろが薬は毒だ気のパワーで治せ、みたいなヤバい民間療法にハマっちゃった時期もあったらしくてねー、まあ何でも金儲けにするヤツはいるからしょうがないよねー。そう話す彼の身体にはもう辛かった日々の痕跡はあまりなく、泣きながら青汁を飲んでいた子供時代なんて想像できないほどだった。
明るく豪気で、話の上手な男性だった。今はどうしているか知らない。
新規のネット指名で行ったマンションの部屋はきれいにしてあり、やや若いお客さんは穏やかそうな人だった。シャワー浴びましょうか、とか言いながら胸元に頬を寄せて、あ、と気がついた。
耳の裏から首にかけて、アトピーの湿疹がちらりと見えた。
「俺は子供のうちだっただけ幸せだよ、大人のアトピーは格段にキツいって聞くからねえ」
いつかあのお客さんが言っていたことをまざまざと思い出す。
浴室で全身を見るとそれは思ったよりも辛そうだ。シャワーの温度をみていると、
「あの、俺ちょっとアトピーひどくてブツブツしてるところたくさんあるんだ。でも、人に移ったりするもんじゃないんだけど……ごめんね」
申し訳なさそうにそう言われた。
目で見てあきらかなことを改めて言葉にして伝えてくれたことに、誠実だ、と感じた。
石けんがついても大丈夫ですか?と『まったく深刻に考えていません』という口調を作ってきくと、うん大丈夫だよ、と答えてから彼は「洗ってくれるの?」と怪訝そうに言った。そこに『触れるの嫌じゃないの?』のニュアンスを感じて「もちろん!」とできるだけ軽く明るく返事をすると、敏感肌用と書かれたボディソープのボトルを渡してくれた。ありがとね、と言って。
よかったうまくやれそうだ、と思った。ベッドに移動するまでは。
白いシーツに、猫が引っかいた痕のようについた細く鋭い茶色の模様を、血なのだと理解するまでは。
あからさまにならないよう気にしながら、生まれて初めてアトピー性皮膚炎の患部を間近に見てわたしは身構えた。
この斑模様は痣ではなく傷なのか、点や線状に血がにじんだものの集合にみえる。肌荒れや吹き出物や、例えばムダ毛の処理をしたあとの赤い飛沫のような内側の出血とは全く違うんだ。これはもっと、引っかき傷に近いものなのかもしれない——。
直の体液となると、急に怖くなった。今日はわたしに切り傷も口内炎も、性器を酷使した時特有のひりつき感も何もない。でも、彼の身体と触れ合うことに躊躇した。
わたしが移し移されたくないものは、アトピーじゃないんだよ。もしもそう告げたとしたら、彼はなにを思うだろうか。あんな風に言ってくれた人だから、もし性感染症の話をすればそれは切実な問題だと理解してくれるかもしれない。でも、だからといってこの場でわたしの口からそんなことは、やはり言えはしない。
考える時間がほしくて、キスをしようとした。
顔を近づけると彼がわたしの耳にそっと触れ、消えそうな声で、あ、緊張する、と呟いた。どうして、と笑ってささやきながらモヤモヤとした気持ちがこみあげて、振り払うように腕を回しそして唇をつけた。それからもう少し強く抱きしめた。
余計なことを考えちゃだめだよ、この人はわたしを信頼してお金を払ったんだよ、と自分に言い聞かせる。でも、大丈夫だろうと見積もる気持ちを、やっぱりなにかが邪魔してしまう。
傷のない部分の肌にそっとさわると、反応する場所を見つけた。舌の表と裏を使って上手く舐めてあげたらすごくいいんじゃないかと期待がふくらむような手応え。
上下の唇を自分の唾液で濡らして、揺れるように滑らせてみた。願った通りの小さく切ない声が聞こえる。とても嬉しいのに、それでも舌を出すことはできなかった。
わたしを見上げる彼の視線がまだ『触れるの嫌じゃないの?』と言っているかのように勝手に感じてしまう。
内心の奥に隠した『舐めるよりは』という判断を、投げ捨ててしまいたかった。その病さえなかったら、という気持ちを拭えないままでよそよそしい愛撫を続けた。よそよそしさが伝わらないようにすることに、一生懸命になっていた。
ペニスには目に見える炎症がなかった。心の底からホッとした。
全部が終わって、それじゃあ行くね、と荷物を持つと、彼が「今日は本当にありがとう、すごく楽しかったです」と軽くおじぎをした。荷物をまた床に置いてぎゅっと抱きつく。
服を着ている彼が、その身体が、無性に愛しくてたまらなかった。
安全なバリアが一枚あるだけで、わたしの心はこんなにも素直に彼を抱きしめられるのか、と思った。
「あの……また指名してもいいかな」という声がして、うなずいた。玄関でもう一度キスをして別れた。
本当にまた指名されたら今度はどうしよう、と考えながらエレベーターに乗り込んだ。彼の爪が耳の裏を掻くジャリジャリとした音が頭に甦る。マナーを守ってくれるお客さんは大切な存在だし、もっとよいプレイをして優しいあの人に楽しんでほしい気持ちも確かにある。でも。
そして突然に思い出した。あのとき、あのお客さんの苦労話に自分は「怖い」と言ったのだ、ということを。そうだ、たしかにそう言ったのだったなあと。
真夜中のエレベーターでゆっくりと落下しながら、わたしはぼんやりと後悔していた。


- 職種
売り専です…お客さんも売る側のスタッフも男性の風俗です
自己紹介
大女優とも呼ばれています。気づいたらもうすぐ40歳。なんとか現役にしがみついています。
好きなものは、コーラ!!
皆さまの中には聞いたことがない仕事かもしれません。いろいろ聞いてくださると嬉しいです!!


- デリヘル嬢。
ここでは経験を元にしたフィクションを書いています。
すきな遊びは接客中にお客さんの目を盗んで白目になること。
苦手な仕事は自動回転ドアのホテル(なんか緊張するから)。
goodnight, sweetie http://goodnightsweetie.net/


- 元風俗嬢 シングルマザー
風俗の仕事はだいたい10年ぐらいやりました。今は会社員です。
セックスワーカーとセクシュアルマイノリティー女性が
ちらっとでも登場する映画は観るようにしています。
オススメ映画があったらぜひ教えてください。
あたしはレズビアンだと思われてもいいのよ http://d.hatena.ne.jp/maki-ryu/
セックスワーカー自助グループ「SWEETLY」twitter https://twitter.com/SweetlyCafe


- 非本番系風俗中心に、都内で兼業風俗嬢を続けてます。仕事用のお上品な服装とヘアメイクに身を包みながら、こっそりとヘビメタやパンクを聴いてます。気性は荒いです。箱時代、お客とケンカして泣かせたことがあります。