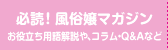HOME > 風俗嬢コラム Worker's Live!! > 元気ですか
| 元気ですか |  |
|---|
でもあたし高校の時のあだ名バッジョだよまじ超ウケるっしょ、とひと息に言ってレオナちゃんが自分で笑った。なにそれ、やばいね、と言いながら私とミクちゃんも遠慮なく笑った。
秋の台風はまだそれほど近づいていないはずだったが、雨はうっとおしく降っており、さっぱり仕事の来ない待機室で「高校生のとき、彼氏いた?」というまったくしょうもない話からはじまった。
私は引っ込み思案な性格ゆえ地味な学生生活だったし、ミクちゃんもこれといった思い出はないなぁと言う。
そこへレオナちゃんがお坊ちゃま進学校の美男子と付き合っていたという事実を明かしたものだから、なんという勝ち組発言、悪いオンナだわ、とふたりして大いに盛り上がったところ「バッジョ」発言が飛び出したのだ。
ちょっと待って、なにそれ、なんでそんなことになったの。
「いや、理由は一応あんだよ、あんだけど今ちょっと待って。あのね、とにかくコードネームみたいなもんが全員にあったの!バカとしか言いようがないっしょ?うるせえ女子高生だったワケですよ。そんなんでさー同じ学校内で恋愛とか始まる訳もなくて、あたしそのカレシの前では超おとなしいお嬢様キャラぶってたんだよ、あはははは。そいで本性がバレるの超おびえてて、外であたしのことバッジョつったヤツぜってーぶっ殺すかんな!ってゆってた」
またしても自分でいちばん笑うレオナちゃんの高校生時代が、なんだか容易に想像できた。きっと今と同じように気さくで元気いっぱいで、たくさんの明るい友達を周りに従えきらきらした毎日を送っていたんだろう。
「でも、変なあだ名だったらあたしもけっこうヘンかもしれない。自信ある!」
と、そこでミクちゃんが言った。聞き役になることの多いミクちゃんが、はにかみながらもいつになく元気に主張したので、レオナちゃんと私は揃って目を輝かせた。なになに聞きたいー。
「あっ、でも、ただの本名っていうか、本名の一部なんだけど……」
だけど次にミクちゃんはそう言って、だから私たちは慌てて遮った。あっそっか、そうなんだ、じゃあだいじょぶだよ、本名言いたくないよね、うんうん。
「ううん、ふたりだったら大丈夫。あたし名字が野村なんだけど、ずいぶん長いことノムさんって呼ばれてたの。変じゃないけど、でも、すごく変だよね?女の子には普通……呼ばないよね!?」
私は吹き出し、レオナちゃんはげらげらと笑った。ごめん、あまりにも似合わなさすぎておもしろいよ!
「小学生の時からノムさんで……でも別に疑問とか持たなかったの、幼すぎて。高学年あたりからあれ?って思い始めて、でも今さら変えてくださいとも言いにくくて。エスカレーター式の学校でね、こう、生まれ変わるチャンスがなかったの。でもうちのお父さんも会社で部下のひとにノムさんって呼ばれてるの聞いて、なんかもうすべてがね……うん……うふふ」
思春期のミクちゃんが悩む姿を想像すると愛おしくて、そして頬を染めてたくさんしゃべってくれる今の彼女の姿が嬉しくて、私は口を開いた。
聞いちゃったしあたしも言うんだけどさ、あたしの本名って……
そこまで言った時、あっ!!と今度はミクちゃんがさえぎった。ごめん、あたしそんなつもりで言ったんじゃないよ、あたしのを知ったからって、言ってくれなくていいんだよ、ごめんねぇ、と。
聞いちゃったから自分も、だなんて余計な言い方しなければよかった、と後悔していると、
「ミクちんは本当にいい子だねえ〜」と、わざと芝居調に言って、レオナちゃんが取りなした。「そういうつもりじゃなくて、フッツーに、だいじょぶってこと、だよね?」
目配せされて私は首をぶんぶんと振る。うんうん、いいのいいの。話したいの、言わせて。
あたしの本名って、マサコ、なのね。古臭くていやなんだけど、そのうえ漢字で書くと昌子、なの。日曜日の日を縦に2つだからさ、男子にヒヒコだヒヒコ!!って囃し立てられてさー、ほんとうるさかったんだよねー。まあ、それだけなんだけどさ。
小学生の男子ってすぐそういうこと言うよね、とミクちゃんは顔をしかめ、でもマサコって名前かわいいと思う、響きがあったかいもん、と言った。
ヒヒコ、ってのもなんか格好いいじゃん、アフリカとかどっか山奥の民族の、戦いの女神とか女王様の名前みたいだ。レオナちゃんはそう言って、ハリセンボンの人がやる『エジプトの壁画のポーズ』で笑わせた。
夕方にほんの数人のショート客を迎えた後はもはや開店休業状態で、私たちのおしゃべりは続いた。
進学校の男子とは、じきにおしとやかなフリに疲れてしまってお別れしたこと。
待ち合わせに必ず早く行き、毎回同じ文庫本を読んで(読むポーズをとって)彼を待っていたこと。このエピソードで涙が出るほど全員が笑った。好きだったんだねえ、と言いながら。
彼に別れを切り出すと「ナツキちゃんは社交的な女の子だから、僕みたいな男じゃつまらないよね、ごめんね」と言われたこと。やっぱ無理はするもんじゃないね、と笑い飛ばしてから、あっそうそうあたしのカワイイ本名は夏希ちゃんだからね、よろしくぅ〜。と付け加えていた。
バッジョの由来は、ふたりで頼み込んで頼み込んで、やっと口を割ってくれた。
3人の御曹司に貢がれるより、本当に愛する人ひとりとサバイブしてみたい、とある時口走ったのだそうだ。絶対なにかのマンガに影響されてたんだよ、としつこく念を押していた。
それをたまたまサッカーに詳しい友だちに聞かれ、それってロベルト・バッジョという世界的カリスマ選手の「3回の平凡なゴールより1回の華麗なゴール」って名言にそっくりじゃん、といたくウケたのが最初なんだそうだ。
ひいひい笑いながら「で、今でもそう思ってるの?」と尋ねてみると、まさか!と声を荒げていた。
お父さんのほうのノムさんは、もうこの世にいないこと。
いつのころからかお酒の量が増え、根っからの医者嫌いが祟ってあっという間のさよならだったこと。
泣いて頼んででも病院へ行ってもらっていれば、と、今でもつい考えてしまうこと。
でもきっとお父さんはそのへんに浮かんで、悩ませてごめんなって言ってるよ、とやたら真顔になって言うと、ミクちゃんも「お父さん今のあたし見たらびっくりするかな」なんて言うので、いやいや、たくましく生きてくれてありがとうって言うでしょうよ、と無責任に前向きな意見を私は述べた。
レオナちゃんは「ノムさーん、金持ってる客2、3人頼むよ」と空中に話しかけてまたも笑いを取っていた。
帰り際に、小指をそっと立ててミクちゃんが言った。
「今日きいたこと、ふたりの秘密……って言うと大げさだけど、ぜったい誰にも話さないね」
そのかわいらしい仕草に胸打たれながら、私も小指をそっと挙げた。約束。
嬉しかった、と私は言い、照れくさそうにレオナちゃんも続いた。
『名前なんていうの』
客にそう訊かれるたび、私の脳裏をあの日の午後がほんの一瞬で通り過ぎる。
あのとき聞いた名前を実際に使うことはなかった。万が一にもどこかで口が滑ったら大変だし、誰も呼び合うつもりで口にした訳ではない。ただ、バッジョ、という言葉だけは生き残って、やあ、イタリアの至宝、などとレオナちゃんに呼びかけることはあった。バッジョのウィキペディア読んで勉強してんじゃねーよ!とその度おこられ、また一緒に笑ったものだった。
どういうわけか、あれから月日はとめどなく流れてしまった。私はまだこうして同じ仕事を続けている。
元々仲良くやっていた私たちはあの日以来さらに、仕事の合間に他愛ない言葉を掛け合うことが小さな楽しみとなった。だけど、店が突然なくなったのは2ヶ月ほど後だっただろうか。
摘発されたのかなんなのか、説明は一切なされず、ただ無店舗型のデリバリーヘルスとして営業を再開するという知らせを受けた。
新店は高級志向でというのが経営陣だかの意向で、キャストの容姿や接客のレベルを上げ、高めの料金を取る予定だ、ということも。
雇っていた女子全員に声をかけている訳ではないので、万が一旧キャストの連絡先を知っている者もこのことは内密に、と釘を刺された。
そしてオープン後の新しい店で、彼女たちに会うことはできなかった。
私は、ミクちゃんの電話番号だけ何かの折に入手していた。
何度か迷った。が、ついに私は彼女へ電話をかけることもショートメールをすることもできなかった。もしもレオナちゃんが私の立場なら、なにか上手な文面を考えて誰も傷つかないように近々お茶でも飲もうよなんて誘えただろうか。でも、私は、うまくできなかった。
『店での名前じゃなくて、本当の名前だよ。源氏名ってなんだか味気ないじゃない?商売って感じがしてさ。わかる?男っていうのはロマンチストなんだから、意外と気にするものだよ?そういうことをね。男心を勉強しなさい』
客の猫なで声に、私は曖昧に頷く。貴方って、とても純粋なひとなのね、と。
あの日、私は言わなかった。
本当は、囃し立てられる、なんて程度のからかいではなかったこと。複数の男子に囲まれ、お前が触った物はヒヒコ菌がついている、と言われ、バケツの水をかけられたこと。教師が口にした「男の子たちはアナタと仲良くしたいんじゃない?」というアドバイス。一度だけ連れて行かれた児童精神科のドアの色。
でも、言わなかったけど、大丈夫だった。
あのときから何度反芻したか分からない、ふたりの優しい言葉。その度に、古代アステカかどこかの勇敢な美女が微笑んでくれる気がした。
『俺はね、そのへんの客みたいに、キミのこと金でどうこうしたいとは思ってないんだ。こう見えて紳士だからね、嫌がることはしないし、ね? 一緒に気持ちよくなりたいって思ってる。男と女はそれが一番大切だろう?』
いろんな相手から100回は聞いたかと思う台詞を得意げに放つ男の顔を見上げ、そう?そんなふうに思ってるの……?と俯きながら私はつぶやく。
赤く染めた頬と潤んだ瞳と、あの頃よりも少しは上達した演技で。
ねえ、恥ずかしいから、絶対内緒にしてね。あたし、本名はミホ、っていうの。……ふふ、よくある名前でしょ?
『ミホっていうんだね。ミホ、さあおいで。ほうらもっと脚を開いてごらんミホ、そうだ、もっと気持ちよくなっていいんだよミホ、ああ、綺麗だよミホ、ああミホ、もっと感じていいんだよ、ほらもっと声出してミホ』
いや、あの時どんな言い方をしていたって私たちはまた会えたのかもしれない、ふたりは確かに寛容な人たちだった。だけど目の前でなにかが壊れることを酷く恐れて、足が竦んだのだ。私は、女ともだち——と呼んでいいのかも未だに気が咎めてしまう——という生まれて初めてのささやかな幸せの前で、情けなく弱かった。
男の喘ぎ声と私の喘ぎ声が、殺風景な部屋にあてもなく浮遊している。その隙間を縫って、元気ですか、と窓辺へ向かい念じてみる。レオナちゃん、元気ですか、ミクちゃん、元気ですか。どこかでサバイブ、していますか。
夜の空間をスルスルと泳ぎ出したその声は、けれどそう遠くまでは行けずに消えてしまうだろう。
街には何度目かの秋がまた来ていて、今夜も雨が降っている。私は、元気です。


- 職種
売り専です…お客さんも売る側のスタッフも男性の風俗です
自己紹介
大女優とも呼ばれています。気づいたらもうすぐ40歳。なんとか現役にしがみついています。
好きなものは、コーラ!!
皆さまの中には聞いたことがない仕事かもしれません。いろいろ聞いてくださると嬉しいです!!


- デリヘル嬢。
ここでは経験を元にしたフィクションを書いています。
すきな遊びは接客中にお客さんの目を盗んで白目になること。
苦手な仕事は自動回転ドアのホテル(なんか緊張するから)。
goodnight, sweetie http://goodnightsweetie.net/


- 元風俗嬢 シングルマザー
風俗の仕事はだいたい10年ぐらいやりました。今は会社員です。
セックスワーカーとセクシュアルマイノリティー女性が
ちらっとでも登場する映画は観るようにしています。
オススメ映画があったらぜひ教えてください。
あたしはレズビアンだと思われてもいいのよ http://d.hatena.ne.jp/maki-ryu/
セックスワーカー自助グループ「SWEETLY」twitter https://twitter.com/SweetlyCafe


- 非本番系風俗中心に、都内で兼業風俗嬢を続けてます。仕事用のお上品な服装とヘアメイクに身を包みながら、こっそりとヘビメタやパンクを聴いてます。気性は荒いです。箱時代、お客とケンカして泣かせたことがあります。